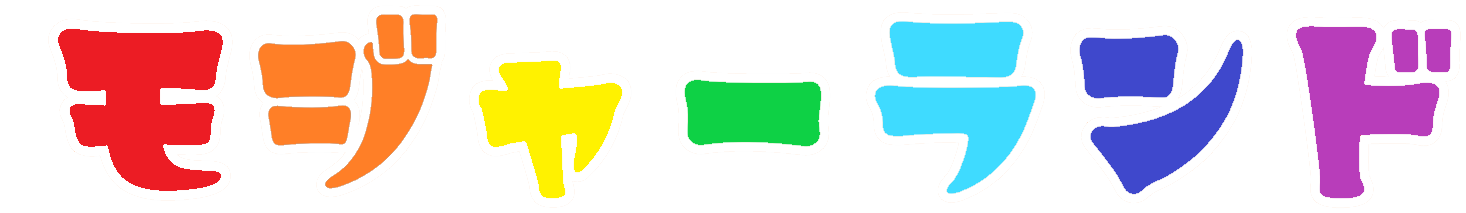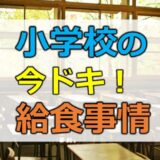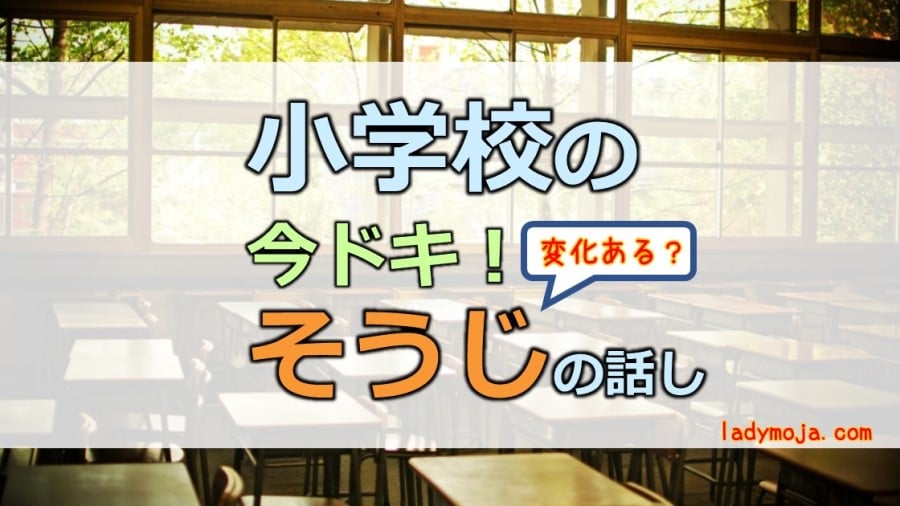
自分のときもそんなに覚えてないけど、今の小学校の掃除ってどうなってるんだろう?
やらないこととか、変化ってあるのかな。そんな疑問をもって子供に聞いてみた結果を、まとめてみました。
これから1年生になる子供をもつ人にも参考になりますよ。
ふだんはあまりわからない、他の小学校の中をのぞく感じでみてみてくださいね♪
小学校そうじの場所と内容
わたしの子供の小学校は昼休みのあとに、20分そうじの時間があります(ずっと同じ音楽がなっている)
1週間交代で、祝日は無視して必ず1週間交代なんだとか!
大変なそうじ場所のときに祝日があると、ラッキー!らしいです・・・
トイレ
トイレそうじは3年生から!!
1年生教室横のトイレでも高学年の担当(みんなのトイレなので)

人数は5人くらい。
A:流し台を洗剤たらしてスポンジで洗う
B:便器を洗剤をたらしてトイレたわしでこすって流す
C:ドアノブや便座などを水拭きして、乾拭き
みんな終わったら壁をふいたり、ふかなかったり。
トイレの床は流さなくてもいい洗剤エキスを作り、デッキブラシでこすると言っていました。
下駄箱

5人くらい。
小さいほうきとちりとりで、靴箱の砂をとって…
すのこをはがし、下の砂をはいてあつめます。
教室の床をはく
5人くらい。
教室そうじ係りが机を下げて、ほうきではく。
ゴミ箱のゴミは、教室係のはき係が袋をむすんでゴミ捨て場へもっていきます。
履き係orふき係のどちらかが黒板の粉をミニほうきでとります。
教室の床を拭く
5人くらい。
クラスによって違うが、水拭きは金曜だけ(休日の前)
あとは乾拭きで「ダダダー」と床にぞうきんをあてて、手でふいていきます。
教室の窓
ふだんはやらなくて、大そうじのときしか拭かないみたいです。
廊下&流し台

教室と同じで履いてから濡れたぞうきんで拭き、流し台をたわしでこすってキレイにします。
誰が床を拭くか決まっておらず、交代でやっているみたい。
ずっとはく方が楽でいいから、次の日も…ていうのはナシでみんなで自主的にかわりばんごでやっているそうです。
1年生のお手伝い
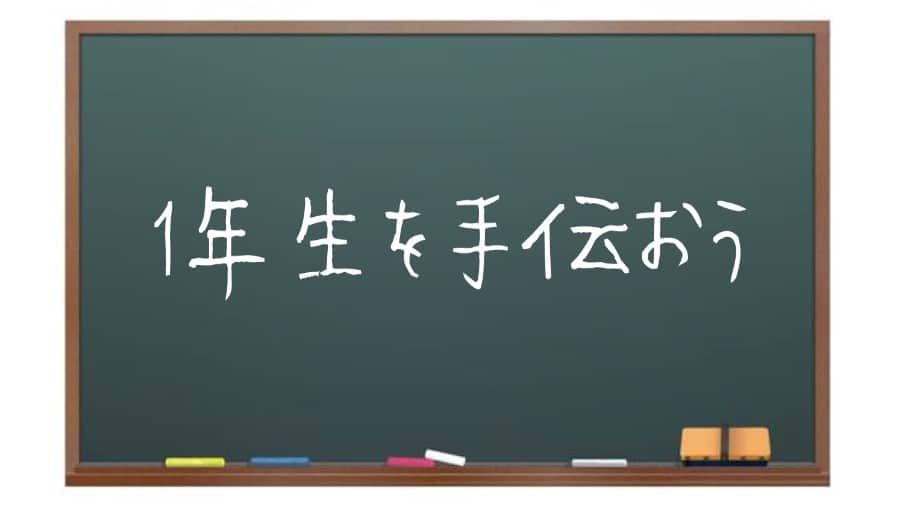
クラスによって担当する人数は違いますが、3人~8人が1年生の各それぞれのそうじ場所を手伝いにいきます(これも当番で1週間交代)
1年生で入学したてでちゃんとできなくても、6年生がいるから心配しなくても大丈夫!
「教室行ったらよってくるよ」と小6の息子が言ってました。弟がいるので小さい子供の扱いになれてるから…人気者なのかな。
息子の友達は「あだなで呼ばれるからイヤ~」って言ってたらしい。1年生も人を見て近づいてくるんですねぇ。
こうやって自然に交流して学んで、いつのまにかできるようになっていくのでしょう。
【まとめ】小学校のそうじはあまり変わっていなかった
時代の流れで「やらないこと」が増えているかな~って思ったのですけど(トイレ掃除とか床ふき)意外や意外あまり変わってない事実がわかりました!
自分が使っているものは自分で掃除するという、情操教育がちゃんとされててよかったです。
(※情操教育とは…感情や情緒を育み、個性的な心の働きを豊かにするためとされる教育のこと)
小3の子供もトイレそうじをちゃんとやってて「ほっ」としましたよ。と同時に「ちゃんとやってるんだ~」と感心しました。
しかも6年生が1年生の手伝いをするのですねぇ(わたしのときは覚えていないっ!)
コロナの時代で6年生と1年生が交流する行事もすべてなくなってしまったので、これだけでもちょっとした交流じゃないでしょうか。
今と昔の差はほとんどなくて、正直よかったです!
小学校に行く機会もないので、やはり聞いてみないとわからないことばかりですね。
他の割と変化していた話しも書いているので、ぜひのぞいてみてください♪
▼その他小学校についての話し▼